このサイトはアフィリエイト広告を利用しております
- 紅芋の香りに、杜氏の心を映す。静かな熱を宿した、宮崎・飫肥の手造り焼酎
- 杜氏潤平とは?宮崎・飫肥の地が育む手造り焼酎の傑作
- 小玉醸造の歴史と再生物語
- 手造り麹のこだわりと白麹の力
- 宮崎紅の力:原料芋が生む華やかさ
- 麹米と仕込み水:自然が生むまろやかさ
- 造りの工程:伝統を守りながら進化する焼酎造り
- 味わいのプロファイル:甘く、丸く、清らかに
- 飲み方別テイスティング:温度で変わる多層的な表情
- 料理との相性:食中酒としての完成度
- 香りの専門分析:果実香と焼香のハーモニー
- 限定性と季節入荷:毎年“待たれる”手造りの味
- 杜氏潤平シリーズ比較:多彩な個性と味わいの広がり
- 杜氏・金丸潤平氏の人物像:情熱と哲学
- 宮崎焼酎の中での位置づけ
- 受賞歴と専門家からの評価
- 消費者レビュー・実際の声
- 保存方法と味の変化
- 市場と入手難易度
- 宮崎焼酎文化との関係
- 総評:静かな情熱が醸す、人に寄り添う酒
紅芋の香りに、杜氏の心を映す。静かな熱を宿した、宮崎・飫肥の手造り焼酎
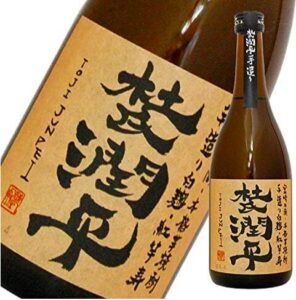
宮崎県日南市、飫肥の静かな町に佇む小玉醸造。
その蔵で杜氏・金丸潤平氏が丹念に手造りで醸す芋焼酎が「杜氏潤平」です。
紅芋「宮崎紅」の上品な甘みと白麹のやさしい酸味が調和し、
口に含むとほのかな果実香とともにやわらかい余韻が広がります。
その味わいは、どこまでも穏やかで、飲む人の心を癒すよう。
燗でもロックでも、その日の気分に寄り添う一杯です。
蔵人の誠実な仕事が息づくこの焼酎は、
派手さではなく、確かな温もりで人々の暮らしに寄り添います。
一口で、宮崎の空気と人の情が伝わるような、優しい手造りの味です。
杜氏潤平とは?宮崎・飫肥の地が育む手造り焼酎の傑作
「杜氏潤平(とうじじゅんぺい)」は、宮崎県日南市飫肥(おび)にある小玉醸造が造る芋焼酎。
アルコール度数25度、容量720ml(または1800ml)で、紅芋「宮崎紅」と国産米を原料に使用。
その味わいは、華やかな香りと柔らかな甘味が特徴で、口に含むとふわっと果実のような香りが立ち、
後味は驚くほどすっきり。飲み疲れしない清らかな印象が残ります。
一方で、ただ軽いだけではなく、芋本来のコクと香ばしさも感じられるのが魅力。
まさに「手造り焼酎のやさしさと深み」を兼ね備えた逸品です。
毎年の限定入荷のたびに即完売するほどの人気を誇ります。
小玉醸造の歴史と再生物語
宮崎県日南市の小玉醸造は、明治初期に創業し、長い間地域に愛されてきた老舗蔵。
しかし一時は時代の流れに押され、製造を休止。蔵の灯が消えかけた時期もありました。
転機は2001年。現当主であり杜氏でもある金丸潤平氏が、
「地元の味をもう一度甦らせたい」という思いから蔵を再興しました。
彼は東京での修行を経て帰郷し、先代の手造り製法を現代に蘇らせます。
再び木桶を使い、麹を人の手で育てるという、手間のかかる伝統的手法を貫く姿勢は、
今や日本全国から高く評価されています。
小玉醸造は、“規模よりも質”“効率よりも誠実さ”を信条とする、
宮崎焼酎界の魂の蔵といえるでしょう。
手造り麹のこだわりと白麹の力
杜氏潤平の美しい味の根幹にあるのは、「手造り麹」という徹底したこだわりです。
現代の多くの蔵が機械麹を導入する中、
小玉醸造では今も木桶を使い、人の手で麹を混ぜる伝統を守っています。
白麹菌を用いた造りは、やさしい酸味と柔らかな甘味を生み出し、
紅芋の華やかな香りを引き立てる効果があります。
麹室(こうじむろ)の温度や湿度の管理はすべて杜氏自身の感覚に委ねられ、
気候や芋の状態に合わせて微調整されます。
この“人の勘と経験”こそが、工業的製法には出せない奥行きを作り出しています。
「手で触れ、香りを聞き、麹を育てる」。
この言葉に、杜氏潤平の酒造りの哲学が凝縮されています。
宮崎紅の力:原料芋が生む華やかさ
杜氏潤平に使用される主原料は、宮崎県産の「宮崎紅」。
糖度が高く、繊維質が少ないため、甘く上品な香りを放つ紅芋です。
蒸した際の香りは甘い焼き芋やカスタードのようで、
焼酎に仕上げると南国果実のような香気が加わります。
この芋の特性を最大限に引き出すため、
小玉醸造では蒸留温度を極限まで低く設定し、繊細な香りを逃さない工夫をしています。
結果として、杜氏潤平は芋焼酎でありながら“フルーティーで軽やか”という独自の個性を獲得。
女性ファンが多い理由も、この香りのやさしさにあります。
麹米と仕込み水:自然が生むまろやかさ
焼酎の品質を左右するのは、原料芋だけではありません。
小玉醸造では、麹米に宮崎県産米を使用し、仕込み水には飫肥の天然湧水を使用しています。
この水は軟水で、口当たりが非常にまろやか。
ミネラル分が少ないため発酵が穏やかに進み、
柔らかく澄んだ味わいを生み出します。
杜氏潤平の“すっきりとしたキレの中に優しさがある”という味わいは、
この水の性質と手造り麹の組み合わせによるものです。
宮崎の土地が生み出す芋と水、そして人の手が融合した時、
初めてこの酒が完成するのです。
造りの工程:伝統を守りながら進化する焼酎造り
杜氏潤平の製造工程は、まさに“伝統と革新の融合”。
蔵では、創業時から使われてきた木桶や甕を大切に使用しながら、
現代的な衛生管理を取り入れた“新しい手造り”を実践しています。
まず、原料の宮崎紅芋は一本一本手洗いされ、皮を残したまま蒸されます。
この「皮ごと仕込み」により、香ばしさと奥行きのある甘みが引き出されます。
麹造りは全て人の手によって行われ、
室内の温度・湿度・時間の変化を感覚で見極めながら発酵をコントロール。
仕込み水には飫肥の湧水を使い、じっくりと発酵を進めます。
蒸留は常圧蒸留。
高温で香りを飛ばさず、旨味と甘みを保つために、低速でじっくり蒸気を通します。
まさに“手間の味”が詰まった焼酎造りです。
味わいのプロファイル:甘く、丸く、清らかに
一口含むと、まず感じるのは“香ばしくも華やかな紅芋の香り”。
口当たりは丸く、柔らかい甘味が舌に広がり、
その後にほんのりと白麹由来の酸味が締めてくれます。
甘いのに重くない。
軽やかなのに薄くない。
このバランスが杜氏潤平の真骨頂です。
中盤では焼き芋のような香ばしさと、
南国果実のようなニュアンスが現れ、飲み込む瞬間に清らかなキレが走ります。
余韻にはほのかなミネラル感と、米麹の旨味が残り、
思わずもう一口と手が伸びる――そんな優しい誘い方をする焼酎です。
飲み方別テイスティング:温度で変わる多層的な表情
杜氏潤平は、温度によって驚くほど表情を変えます。
ロックでは、冷却によって香りが引き締まり、
紅芋特有の甘香と白麹の酸が際立ちます。後味はドライで上品。
水割り(5:5)にすると、香りがふんわり広がり、
果実を思わせる甘い余韻が持続。軽やかで女性にも好評です。
お湯割り(6:4)では、柔らかな甘味と香ばしさが全開に。
湯気に乗って立ち上る紅芋の香りは、まるで焼き芋を割った瞬間のよう。
芋の持つ“温かさ”を最も感じられる飲み方です。
ソーダ割りにすると、香りが軽やかに広がり、
柑橘のような酸味がアクセントに。食中酒として万能。
季節や料理に合わせて“温度で遊べる”のもこの焼酎の大きな魅力です。
料理との相性:食中酒としての完成度
杜氏潤平は、“料理の脇役でありながら主役になれる”不思議な焼酎です。
和食では、鶏の炭火焼や豚の角煮、田楽味噌など、コクのある料理と相性抜群。
お湯割りと合わせれば、旨味が何倍にも広がります。
洋食では、クリームパスタやチーズフォンデュなど、乳脂肪系の料理にも好相性。
ロックで合わせると、香りのコントラストが美しく調和します。
さらにデザートとのペアリングもおすすめ。
黒糖アイスや焼き芋スイーツに少量かけると、まるで大人のデザートリキュール。
杜氏潤平は、“食を豊かにする焼酎”という言葉が最もふさわしい一本です。
香りの専門分析:果実香と焼香のハーモニー
香りは、焼酎の命。
杜氏潤平の香りは、単なる芋香ではなく、果実香と発酵香の二重構造で成り立っています。
第一印象は、甘く芳醇な“焼き芋+熟バナナ+バニラ”のような香り。
次に、微細な酸味を伴った“柑橘の皮”のような爽やかさが立ち上がります。
香気成分としては、β-イオノン(紅芋由来の花香)やリナロール(柑橘香)を多く含み、
これが“華やかでありながら穏やか”という絶妙な香気バランスを生んでいます。
蒸留時に香りを飛ばさないよう、低圧・低速で蒸留されているため、
他の芋焼酎にはない繊細な香りの層を持ちます。
まさに“香りを味わう焼酎”。
その静かな芳香は、ワイングラスでも存分に楽しめるレベルです。
限定性と季節入荷:毎年“待たれる”手造りの味
杜氏潤平は、年中いつでも手に入る焼酎ではありません。
手造りによる少量生産のため、年に一度(主に秋〜冬)限定入荷となっています。
芋の収穫期に合わせて仕込みが行われ、蔵の気温・湿度が最も安定する時期に発酵が進みます。
そのため、毎年微妙に味が異なり、ヴィンテージ感覚で楽しむファンも多いです。
また、年によっては「朝掘り」や「別撰酵母」「無濾過」などの特別バージョンが登場します。
どれも通常版とは異なる個性を持ち、
焼酎愛好家の間では“入荷即完売”が当たり前の人気シリーズです。
限定的であるがゆえに、手にした時の喜びもひとしお。
まさに“一期一会の焼酎”と呼ぶにふさわしい存在です。
杜氏潤平シリーズ比較:多彩な個性と味わいの広がり
小玉醸造では、「杜氏潤平」を軸に複数のラインナップが展開されています。
それぞれに個性があり、飲み比べることで焼酎の深みを実感できます。
-
杜氏潤平(定番):紅芋×白麹の華やかで柔らかな味。最もバランスが良く、飲み飽きしない。
-
朝掘り:その年に収穫した紅芋を即日仕込み。香りが瑞々しく、軽やかな仕上がり。
-
別撰酵母:異なる酵母を使い、香気成分を強調。より華やかで芳醇。
-
無濾過:濾過を最低限に抑え、旨味とコクが凝縮。濃厚で通好みの一本。
-
紅潤(こうじゅん):紅芋の香りとコクを極限まで引き出した特別限定版。女性人気が高い。
いずれも「小玉醸造らしい上品な甘み」を核に持ちながら、
個性の違いを楽しめる構成になっています。
杜氏潤平は、シリーズを通じて“香りの表現力”が最も優れたブランドといえます。
杜氏・金丸潤平氏の人物像:情熱と哲学
杜氏潤平という焼酎の名は、そのまま杜氏=金丸潤平氏の名前を冠しています。
彼は1970年代生まれ、地元宮崎で育ち、大学卒業後に東京の酒販会社で修行。
その後、廃業寸前だった実家の蔵を継ぐため帰郷し、
2001年、27歳の若さで蔵を再興しました。
金丸氏の哲学は、「焼酎は土地と人の声を聴くことから始まる」。
毎年、芋の出来や気候に耳を傾け、機械ではなく自分の感覚で仕込みを調整します。
現場では、麹室の温度を手で感じ取り、
発酵タンクの泡の立ち方で熟成具合を判断。
一滴一滴に“命を吹き込む”ような造りです。
また、彼は焼酎を“芸術”ではなく“生活文化”として捉え、
「日々の食卓を豊かにする酒でありたい」と語っています。
杜氏潤平の穏やかで温かい味わいは、まさにその人柄の表れです。
宮崎焼酎の中での位置づけ
宮崎県は今や全国屈指の焼酎王国。
「黒霧島」「赤霧島」「㐂六(きろく)」などの有名銘柄がひしめく中、
杜氏潤平は“手造り蔵の象徴”として異彩を放ちます。
他銘柄が大量生産・全国流通を進める中で、
小玉醸造は“あえて量を追わない”道を選び、品質を最優先。
その結果、宮崎焼酎の中でも“クラフト志向の代表格”として評価されています。
味わいは派手さこそないが、香りの奥行きと余韻の静けさは唯一無二。
宮崎の焼酎が「甘い・まろやか」というイメージを確立した立役者のひとつが、
実はこの杜氏潤平なのです。
受賞歴と専門家からの評価
杜氏潤平は、国内外の焼酎品評会で数多くの賞を受賞しています。
中でも特筆すべきは、**東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)**での高評価。
“香りと味の調和が秀逸”として、複数年にわたって金賞・銀賞を受賞しています。
また、焼酎専門誌『dancyu』『あまから手帖』などでも度々紹介され、
評論家からは「紅芋焼酎の芸術的完成形」と評されます。
さらに、バーテンダーやソムリエからの評価も高く、
“ワインやウイスキーのように香りを楽しむ芋焼酎”として、
カクテルベースにも使われるほどのポテンシャルを持っています。
手造りの温もりと科学的な美しさ――。
それを両立させた杜氏潤平は、まさに**“宮崎が誇る手造りの名作”**と呼ぶにふさわしい焼酎です。
消費者レビュー・実際の声
杜氏潤平は、“芋焼酎ファン”だけでなく“焼酎初心者”にも幅広く愛されています。
SNSやレビューサイトでは、以下のような声が多く見られます。
「香りが華やかで甘いけれど、すっきりして飲みやすい」
「お湯割りにするとまるで焼き芋を食べているような香り」
「芋焼酎の概念が変わった。こんなに優しい味があるなんて」
「ボトルデザインが上品で、プレゼントに最適」
特に女性や日本酒愛好家からの支持が強く、
“香りで楽しむ焼酎”“癒し系の芋焼酎”という表現が多く使われています。
また、リピーターの間では「秋の限定入荷を待つのが楽しみ」という声も多く、
季節を感じる一本として定着しています。
保存方法と味の変化
杜氏潤平のような香り系芋焼酎は、保存環境で味が微妙に変化します。
未開封の場合は直射日光を避け、20℃以下の冷暗所で保存が理想。
ガラス瓶のため光の影響を受けやすく、紫外線で香り成分が劣化しやすい点に注意が必要です。
開封後は、キャップをしっかり閉めて常温または冷暗所で保管。
空気との接触で香りがやや落ち着き、2週間ほどでまろやかさが増していきます。
時間の経過とともに、紅芋由来の甘香が穏やかになり、
代わりに白麹の柔らかな酸が引き立つようになります。
これは決して劣化ではなく、“自然熟成による変化”と考えるべきです。
まるでワインのように、“時が味を育てる焼酎”――
それが杜氏潤平の魅力の一つです。
市場と入手難易度
杜氏潤平は、全国展開されている焼酎ではなく、
主に宮崎県内および一部の特約酒販店のみで取り扱われる限定流通品です。
720mlボトルで1,700円前後、1.8Lで約3,000円が目安。
数量が限られているため、毎年入荷時期にはオンラインショップで即完売となることもしばしば。
地元・飫肥周辺では、蔵元直売所「小玉醸造店頭」でも販売されますが、
その数は限られており、訪問者にとっては“出会えたら幸運”な一本です。
一方で、都市部の老舗酒販店では年に数回入荷があり、
特に秋から冬にかけての「杜氏潤平フェア」などでお目にかかる機会があります。
“追いかけたくなる焼酎”という点で、愛好家の収集心をくすぐる存在です。
宮崎焼酎文化との関係
杜氏潤平は、単なるブランド酒ではなく、宮崎焼酎文化の象徴的存在でもあります。
その理由は、“造り手の顔が見える焼酎”だからです。
宮崎県は、焼酎を「生活の中の酒」として根付かせた土地。
地元の食材とともに味わい、家族や仲間と囲む――その風景の中に杜氏潤平があります。
飫肥という城下町の静けさ、杉の香りが漂う木桶の蔵、
そこに流れる時間そのものが、味に表れています。
この焼酎は、派手なラベルでもなく、流行を追うわけでもない。
けれど、一度飲めば“宮崎の人の優しさ”が伝わる。
それが文化酒としての魅力であり、地域とともに生きる証です。
総評:静かな情熱が醸す、人に寄り添う酒
杜氏潤平を飲むと、最初に感じるのは「穏やかさ」。
香りも味も、どこまでもやさしく、自然で、肩の力が抜けるような温もりがあります。
しかしその裏には、杜氏・金丸潤平氏の静かな情熱と、
何十年にもわたる手造りの技が息づいています。
華やかな紅芋香、なめらかな舌触り、軽やかなキレ。
そのどれもが、計算ではなく“感覚と心”で造られた証。
日常の中でそっと寄り添い、心を和ませてくれる――
杜氏潤平は、まさに“飲む人の人生に優しく馴染む酒”です。
派手な主張はいらない。
ただ静かに、旨く、美しく。
その佇まいこそが、この焼酎の芸術性なのです。
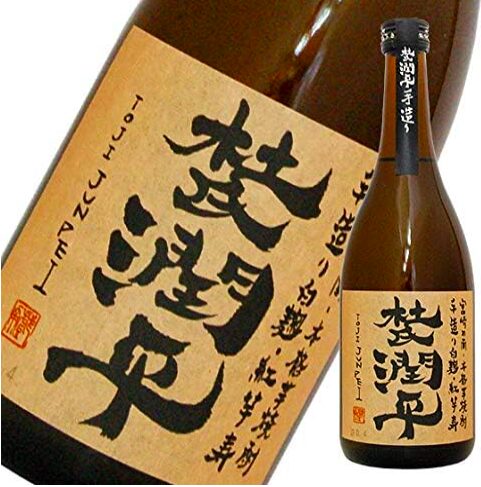



コメント